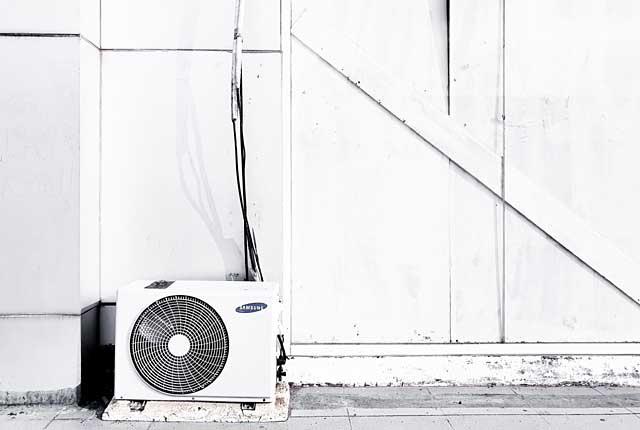あのマザー・テレサの、最後の言葉とは
マザー・テレサはグローバリストでなく、国を大事にする人に思えるお話です。
マザー・テレサは貧困の地に現れた、聖なる慈愛の人で有名です。その最後の言葉はニュースになりました。「息ができない」でした。突然倒れたそうで。
元オスマン帝国、今の北マケドニア共和国出身の、ルーマニア系の人です。
マザー・テレサ批判は生前から始まっていて、ほとんどが大物政治家に対する批判と同じ種類でした。人脈とカネに関するものです。支援者のことや、ノーベル平和賞などの顕彰のことも。
批判されてたんだ
しかし一人の人間として考えると、人は皆、複雑で弱い存在だ以外にありません。本人は自分は善人失格だと自責の念を抱き、貧困国で人々の世話を続ける毎日でした。
ヒトというタイプに生まれた生物の、互助の限界も感じるのです。全ての人間は、理想的な人間ではないという真理です。だから人は人権の概念を設けたのかしらん。
あのマザー・テレサの、最も重要な言葉とは
マザー・テレサの言葉で最重要はこれでした。
「先に自分の国の貧困をなくしなさい」。
そんな発言を?
「異国の貧困者を救う前に、自分の国にある貧困を見過ごしてはいけません」。
「異国での派手な体験を、付加価値として目当てにしてはいけません」。
というような意味でしょう(たぶん)。
「弟子にしてください」という若者が多かったと想像できます。著名人の元へ行けば有名になれるかもと期待して、手伝いに駆けつける者もいたかも知れませんし。
あのマザー・テレサの、自責の念を想像してみると
「まずは自国を富ませなさい」は、行動の合成を意識したものと思われます。人類みんなが自国の内部問題を拡大させなければ、他国との関係も歪みにくい確率です。
貧困から国民の目をそらせるために、他国に意地悪し戦争をしかけるポイントかせぎは、どの国の政治家もやります。政策の動機の大半は、政治家個人の地位安定です。筋を通す信念の人は失脚しやすく、長続きしないでしょう。
国内問題は、他国への暴力に向かいます。内政での失点を外交で埋め合わせる。
だから自国の貧困を軽減することが、国民の責任だと説いたのかも。
人の国境越えは摩擦になるし
国際交流で人種や民族を、スクランブルしてシャッフルする、今のグローバリズム思想のロマンは、口当たりのよいワナだと、マザー・テレサは言ったかに聞こえます。
グローバリズムは、自国ファースト批判して利他主義を装い、国家を乗っ取ります。
どういうこと?
A国がB国に「自国ファースト批判」を吹き込みます。吹き込まれたB国は、是非論争で内部分裂します。分断でスキが出たB国に、A国が入り込んで支配するのです。
2010年代の国際社会は、ナショナリズムとグローバリズムのどっちがワルなのか、言い方のうまさに振り回されました。
マザー・テレサの「自国を何とかしろ」は、グローバリズムとは反対です。
マザー・テレサは、自国ファーストを唱えているのです。
理屈は確かに
マザー・テレサ自身は富裕な家庭出身でした。大事なキーです。それで没後に預金残高が多くて批判が集まりました。
しかし生前の本人は、聖者でも超人でもない自らの非力に、悩みを持ち続けていたと伝わります。人間は機械でないし。通帳残高などに話を小さくしたらだめ。
テレサ自身へのブーメランにもなってる?
「自国の貧困解消に尽くしなさい」をできていない、自分の浮いた孤立にさいなまれていたのでしょう。人類の矛盾を背負っていた面がありそうですね。
東日本大震災の時にも表に出た命題です。炊き出し遠征する芸能人に対して、そんなのは偽善の人気取りだという批判が日本のネットにどっと出ました。
他人を助ける決め手は資金力だから、貧困化した日本で摩擦が強まりました。資産持ちが救世主の栄誉も得るわけで、低所得の一般人はおもしろくない。
日本の海外援助はどう評価する?
昔から、日本は移民に賛成ではなかったようです。人は生まれ育った地で暮らすのがよいから。それで、日本の海外援助は現地にお金を貸して、いっしょに設備をつくります。
建造や製造のやり方を伝授して、向こうの人々の腕が上がるようにもって行くのが、日本が海外援助するパターンです。
現地人リーダーを育成し、産業を育てさせて、売上で返してもらう長期計画です。楽に返せないなら失敗だから、事業計画マニュアルも早くから練ってあります。
経済成長率が高くなって、コスト高が苦でないらしく
以前の日本のやり方は、マザー・テレサとなじみやすい気はします。
他国への支援を悪用すれば、貸金を返済不能にさせて、物納に振り替えて相手国の領土を奪えます。日本がそうしないのは、日本人の「ふるさと志向」もあるのかも。
日本列島の平たんでない雑木林を、かっこうの内需として国土開発して、政府出資の財政で世界2位のGDPに育てた日本人の自信といえました。
国民が力を合わせれば国力は伸びます。土木インフラで力を合わせれば、社会は安定してお国柄も温和になるという方向でした。
その方向性は、江戸時代や平安時代にもさかのぼれますし。
相手国の自助努力を手伝うのが、日本のやり方
日本の海外援助は、国内の方法と似たものでした。中央政府が出費して人々にお金を渡す交換条件で働かせ、経済を順調に回したのが昭和中盤以降でした。
昔の日本の為政者に、国民を故意に貧困にするビジネスモデルの発想がなかったようで。だから日本人は、為政者を倒す必要が常になかったのでしょう。
「何にもない国でも、自分たちで作り込めば楽園に変わるよ」。細かい問題の多い日本の政府開発援助(ODA)は、大筋でマザー・テレサの言葉に近かったでしょう。